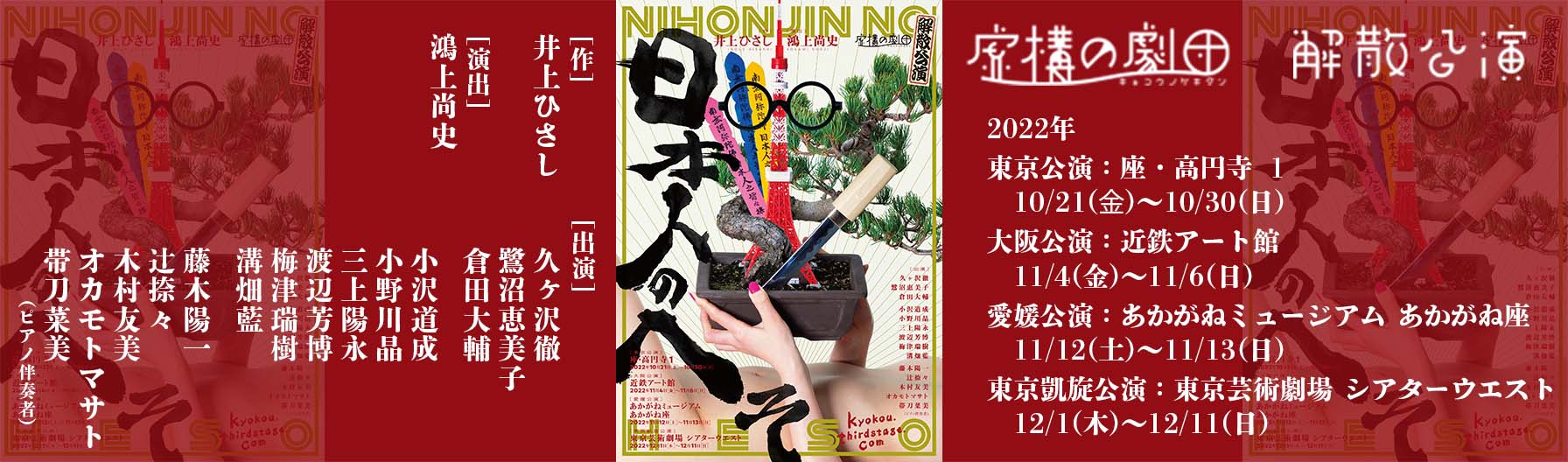こんにちは。牧田哲也です。
また物語を書きました。書きたくないのに書きました。鴻上さんに書かされました。
でも前回書いて思ったんですけど、物語がなかなか書き進まないときの辛さ(僕なんかは体験教室みたいな辛さでしかないですが)とか、書き進むときの無心さは、なにか確実に”一色健治”という役に反映されている感じがして、今回も一応書きました。
前のブログで僕の役は主にあるの女性の恋愛の話を書くと言いましたが、詳しくは恋愛と事件が入った話を書くんです。
なので今回は恋愛と事件を入れた作品を書いたらと鴻上さんに提案してもらって、恋愛と事件を入れた作品を書きました。
一応前回の続きです。
いざ書いてみると、
事件ってなんだ?
って凄く思いました。
これもまた書くことに意味があるので、時間がある人だけ読んで下さい。
『見えない糸』
お互いが手と手を取り合って一緒に歩んで行く…
そんなの理想論。綺麗ごとだ!
あたしにはあれから二年くらいして、新しい彼が出来た。
彼は年下だったけど、もの凄く頼れる人。こういっちゃなんだけど正直前の彼に比べて一緒にいる楽しさには少し物足りなさを感じてはいたけど、自分を持っていて、なにより彼は誰にも見せない顔をわたしにだけに見せてくれる。それはなによりも安心感を与えてくれたし、居心地が良かった。
そんな幸せな日々が続いたある日、彼は交通事故にあった。彼の車に後ろからトラックが激突。彼は一命を取り止めたものの、わたしとの記憶を失ってしまった。
事故などで脳に損傷を受けた場合、新しい記憶を失うことは稀にあるらしい。
その新しい記憶を呼び覚ますためには事故前の生活に戻ることが必要だと医者は言っていたらしい。
今の彼は、わたしがなに者なのかさえ知らない。
でも彼の両親は彼の事故前の生活のひとつであったあたしとの関係を続けること、今まで通り付き合うことを許してくれた。
そしてわたしたちは事故後、初めてのデートをした。
彼はわたしを恋人として認識はしていたものの、病室で少し会った以来ほぼ初対面の状態だった。でもわたしはなるべく事故前と同じように彼に振る舞おうと努めた。
よく出掛けた公園に行ったり、よく出掛けたカフェに行ったり、特別なことではなく、わたしたちの普段の他愛もないデートをした。
わたしは彼のことを、わたしが覚えている限り全部伝えようとした。
楽しかった二人のときのことを思い出せば思い出すほど、今の彼との違いに複雑な気持ちにはなったが、今はなにより彼が昔の彼に戻ることに専念した。
何度かデートをした。
それでも彼は一向になにも思い出さない。だけどわたしは彼のために、自分のために、できることを精一杯やった。
服も当時着ていた、そして彼が好きだった服をなるべく思い出して着て行ったり、
前と同じ香水に戻したり、
少しだけど出会った頃の髪型に戻したり、
細かいアクセサリーだって仕舞い込んでいたものを引っ張り出して身に付けたり、
少しでもなにか思い出すきっかけになりそうなものを見付けては、手当たり次第に使ったし、自分だけでできることも何でもした。
でもその細かい行為が彼にプレッシャーを与えていたのかもしれない。
昔の自分を知ることをだんだんと拒絶するようになった。
『今日はもうこれでやめとこう。』
明らかに自分にも、そしてわたしにも苛立っていた。
わたしは彼を追い込みたいわけではない。なんなら思い出さなくてもまた昔のような関係になれさえすればそれでいいと思っていた。
でも普通のカップルの様なデートをしようとしても昔みたいに会話は弾まないし、昔の彼のことを教える以外会話がなくなってしまっていた。
わたしはどんどん焦るようになった。
彼はわたしと出会う前までの記憶で十分生活は出来ている。
彼はもうわたしとの関係を取り戻したいと思っていないんじゃないか。
わたしは”彼女”ではなく、リハビリのアドバイザーのような存在でしかないんじゃないか。
どこまでどうすれば記憶が戻るかなんて保証はどこにもない。戻らないとこだってある。
あたしはいつものように抱き合いたかっただけだし、いつものような顔を向けて欲しかっただけなんだ。
そんな複雑な気持ちを抱え、わたしは冷静に彼と向き合えなくなっていた。
そんなある日、彼に
『もう会うのはやめよう』
と切り出された。
遂にこの日が来てしまった。
わたしは無力感のなか、『わかった』
としか言うことが出来なかった。
彼は彼なりにわたしのことを考えてくれたのだろう。お互い会っても辛いだけだった。
そしていくら付き合っていた頃の話をされても、今の彼の中ではわたしはただの他人。
好きになった時の感情もわからないし、好きになっていく過程のないまま今のわたしを恋人と受け入れられるわけがない。
わたしのやり場のない気持ちだけが残った。
恋人というのは本当に不思議な関係だ。愛している瞬間は生んでくれた親より大切に思う瞬間だってある。
一度でもそんな気持ちを抱いた相手だとしても、なにかの弾みで簡単にその関係は崩れてしまう。
彼とは事故というどうしようもないことで崩れてしまったわけだけど、
付き合うという行為はお互いの了承の上だけで成り立っているもの。
身勝手な考えではあるが、相手を引き留めておく法律なんてなにもない。
相手が別れたいと一方的に、しかもそれがこちらにとっては理不尽な出来事でも、理不尽なやり方でも、相手に気持ちがなければ受け入れるしかない。
なんなんだろう…
街で見掛けるカップルたちがこんな不確かな”約束”だけで結ばれていることが不思議だと感じてきてしまう。大の大人なのに…
そんなある日、もう会うこともないと思っていた彼から突然電話がかかって来た。
あ~忘れかけていたのに…
忘れてしまった方がずっと楽なのに…
なんでなんだろう…
わたしは微かな希望を胸に通話ボタンを押していた。